ベッド・マットレス通販専門店 ネルコンシェルジュ neruco

すのこベッドとは

ベッドの床板の仕様には「すのこ」「総板」「穴空きパネル」「メッシュタイプ」などがあります。
また「床板」を「底板」「敷板」などと呼ぶことも多いです。この床板の役目は、ただマットレスや布団を支えるだけではありません。
マットレスを安定させるとともに、マットレスの機能や性能を十二分に発揮させるためのものです。
極端な例で申しますが、もし床板がゲル状で、水面のような不安定な状態であったら、乗せたマットレスは充分に性能を発揮できません。
ふわふわ安定せず、まるで暖簾に腕押しのように、反発力も安定しないでしょう。
ですから床板が総板張りであれ、すのこであれ、しっかりマットレスを受け止めているから、わたしたちが寝たときマットレスの恩恵にあずかれるという事になります。
それがベッドの床板は寝心地に影響しているという証なのです。
さてベッドの床板です。この床板を「すのこ状」に、板と板に隙間を設けて使用したベッドをすのこベッドと呼んでいます。
なぜすのこ状にするかというと、湿気の問題があるからです。
日本の気候は、高温多湿の夏が巡るため、ベッドも通気性が悪いとカビの問題が発生します。
よく押し入れにすのこを用いるのも、通気性を確保してカビの発生を防ぐためです。
ベッドをすのこにすると、板が割れるんじゃない?なんて、心配をされる方がいますが、確かにすのこ板の仕様が薄かったり、使う板の枚数が少なかったりするとその心配があるでしょう。
でも、その心配はマットレスを載せるとかなり軽減します。
すのこの板の間隔が7~10cm未満であれば、普通に寝るには何の心配もありません。
ただし、間隔が広めで板が薄く、根太も極細仕様のすのこだと、マットレスを載せないで、すのこ板の支えがない場所に直に乗ることは厳禁です。この場合破損する可能性が高いです。
また、ベッドの上で飛び跳ねたりすることも厳禁です。すのこ板の破損はもとより、コイルマットレスの一か所に一気に衝撃が加わると、コイルが変形しマットレスの性能が著しく劣化します。
すのこベッドの「すのこ」にも、様々な形状、仕様がありその仕様を頭に入れ華奢なすのこの場合は特に丁寧に扱いましょう。
しかしすのこベッドの中には、耐荷重500kg以上を達成している頑丈なものもあります。このような頑丈仕様のすのこベッドは、耐圧分散が低い敷布団も使用することが出来ます。
もうひとつすのこと同じようなベッドの床板に、ウッドスプリングがあります。
床板がマットレスに影響する例として、次にウッドスプリングについて簡単に触れさせていただきます。
ウッドスプリングについて

ウッドスプリング
ウッドスプリングは、ヨーロッパではスプリングスラットと呼ばれています。ちなみにすのこはソリッドスラットと呼びます。
ウッドスプリングはヨーロッパで主流の仕様ですが、床板のスラットを湾曲させたものです。
スラットを湾曲させることにより、すのこのように通気性を持たせ、さらにバネ効果を持たせているのです。
ちなみにスラットは、強度のあるブナの積層材が多く使用されています。
このような難しい仕様がヨーロッパで主流になったのには訳があります。
日本では金属コイルマットレスが主流ですが、欧州ではウッドスプリングとラテックスマットレスなどノンコイルマットレスの組み合わせが80%以上と言われています。
それはなぜか?
その理由は、ヨーロッパでは金属スプリングマットレスが使われなくなったためと言われています。金属スプリングを使わなければクッション性が損なわれます。反発力や耐久性が低下します。
それを補うためにウッドスプリングが発達したものと思われます。
では、なぜ金属スプリングマットレスが衰退したのでしょうか?第一に、金属スプリングマットレスは廃棄とリサイクルがしにくいためです。
金属とウレタン、わた、生地など様々な素材からできている金属スプリングマットレスは廃棄とリサイクルのしにくいものです。
早くから環境に関心が集まっているヨーロッパでは、このために急速に脱コイルマットレスになったものと思われます。
第二に電磁波の問題です。
ヨーロッパのメーカーは電子スモッグという表現をすることがあります。高圧線の下は健康に悪いということは、かつて日本でも言われてきましたが、金属コイルは構造上、電磁誘導が起きやすくなるそうです。
あるいは金属コイルだと地磁気が乱れるという説明をするメーカーもあります。これが確かかどうかは科学的に証明されてはいませんが、疑わしきは…ということではないでしょうか。
ともあれウッドスプリングは、現在ヨーロッパで主流のベッドの床板となっているのです。
すのこVSウッドスプリング
すのこのメリット
- 安価である
- 通気性に優れる
- カビやダニの発生を抑制する
- 安定している
- 寿命がウッドスプリングより長い
- マットレスの性能が素直にでる
などがあります。
すのこのデメリット
- 無し
ウッドスプリングのメリット
- 通気性に優れる
- カビやダニの発生を抑制する
- ダブルクッション効果がある
ウッドスプリングのデメリット
-
- 高価である
- 寿命がすのこより短い
- 振動がベッド全体に伝わる
などがあります。
上記で示した通り「すのこベッド」は良いとこだらけなのです。
すのこベッドは木の材質によって寝心地が変わる
ベッドの床板が寝心地に影響していることは、上記にウッドスプリングとすのこの例で示した通りですが、すのこの素材によっても違ってきます。
すのこベッドは、フレームとすのこを材質を違えている場合が非常に多くあります。
極端な例では、フレームは金属(スチール)で、床板はすのこ板だったりします。
そのすのこも多くが合板ですが、パイン材、杉材、桐材も使われます。
その最も多い事情は、フレームはプリント紙化粧板やメラミン化粧合板など複合素材が最も多く使われているからです。
つまり心材は合板やパーティークルボードが主体です。
パーティークルボードは、木材のチップを加熱圧縮した板のことです。こちらは湿気に弱く、ほかの木材とくらべて強度が低く、粘りがなく、長期荷重でたわみが出るためすのこには不向きです。
ですからすのこは、合板や無垢素材が使われるという事になります。
ベッドの求められる機能や性能を追求すると、当然床板であるすのこにも注目せざるを得ません。
桐材のすのこは湿気に強く健やかな寝心地に影響しますし、パインやヒノキの放香はストレスの解消に効果があるとされています。
つまり、すのこやフレームの素材からの影響も寝心地の中に含まれるという事になります。
すのこに一番多く使われるのはやはり合板です。
合板は、木材の優れた特性をすべて備え、さらに木材の持ついくつかの欠点を製造技術で補正して、木材より強く、幅が広く、伸び縮みの少ない優れた材料に作り上げたものです。
ではその合板はどのように作られるのでしょうか?
先ずベニヤ板から説明します。
ベニヤ板
ベニヤ板は、木の丸太を大根のかつら剥きのように剥いて作った薄い板のことです。厚さは0.6~3mm程度の単層(1枚)のものをベニヤと呼びます。
ホームセンターではラワン材のベニヤが多いと思います。
合板
ベニヤ板を接着剤で積層してできた板を合板と呼びます。
何枚かのベニヤを繊維方向が交互になるように接着し強度を上げています。厚さは用途によって様々ありますが9mm・12mmがメインサイズです。
板のサイズはサブロクサイズと呼ばれる、910×1820mmが基本です。またシハチサイズとよばれる1220×2430mmのものもあります。ともに尺寸の呼び方でサブロクは3尺×6尺の略称です。
コンパネ
ついでによく言われるコンパネについて述べます。
コンパネは合板の1種です。コンクリートを流し込むときのコンクリート型枠として使用されるものです。コンクリートパネルとも呼ばれています。これを略してコンパネです。
普通の合板とは違って板の基本サイズが900×1800mmになっています。厚さは12mmがほとんどです。
上記に示した通り、合板は、木質の繊維が縦横に何層にも重なっていますから、強さの面ではダントツです。すのこに最も適した耐久性があります。
無垢材は曲がりが少なく、すぐ折れてしまいますが、合板であれば少しくらいの曲げではしなるだけで折れることはありません。
桐やヒノキ、杉やパインがすのこに使われる理由
ですが哀しいかな、桐やヒノキの持つ独特の風合いや効能は持っていません。ここに桐やヒノキ、杉やパイン材すのこに使われる理由があるのです。
それでは次に、ベッドフレームにはどんな材料が使われていて、それぞれどんな特徴があるのでしょうか?
そこのところを簡単にご説明します。
ベッドフレームに使われる材質の種類と特徴
- 木質系(ウッドフレーム)
- スチール製(スチールフレーム)
- レザー製(ウッド+レザーフレーム)
- ファブリック製(ウッド+ファブリックフレーム)
1.木質系(ウッドフレーム)

木質系ウッドフレームとすのこの床板
ベッドフレームの素材として最も使われているのが木質系です。木は温かみがあり、どんなインテリアにも合わせやすいのが特徴です。
ウッドフレームには、天然木無垢材を使用しているものと、パーチクルボードや合板に、木を薄くスライスした突板を貼り合わせたものや、プリント紙などを貼った化粧合板ボードがあります。
無垢材は使い込むうちに風合いが変化し、経年変化を楽しむことができます。突板も表面は本物の木なので質感は高いです。
それに対して、プリント化粧板とメラミン化粧板は、カラーリングや木質を印刷したものですが、2つの違いは以下の通りです。
プリント紙化粧板は、薄葉紙(ウレタンコート紙や強化紙)と基材である合板や木質繊維板(パーティクルボードやMDF)とを貼り合わせた化粧板です。
単色や木目調など、デザインが豊富で表面保護のための仕上げ塗装が施されているため、手入れが簡単です。
メラミン化粧板は、メラミン樹脂含浸紙とフェノール樹脂クラフト含浸紙のみを積層して熱圧成型する厚さ1mm程度の樹脂化粧板です。
やはり基材である合板や木質繊維板(パーティクルボードやMDF)と貼り合わせて使います。
メラミン化粧板の特徴は、優れた耐久性と単色や木目調など、デザインが豊富でお手入れが簡単です。
無垢材などに比べると価格はリーズナブル(プリント化粧板と比べると高い)です。
2.スチール製(スチールフレーム)

スチール製スチールフレームと木質のすのこの床板
スチールフレームは、比較的安価で部材が空洞であるため軽い素材であることが特徴です。ほかに、パイプベッド、アイアンベッドなどと呼ばれています。
軽い素材のため組み立ても容易です。移動も楽なため頻繁に模様替えをしたい人にもおすすめです。
ただし無理やり引きずると、床を傷める可能性があります。
その場合市販の「カグスベール」を脚の先に貼っておくと、抵抗なく滑らすことが可能です。あるいは段ボールを10cm四方程度に切って、脚の下に挟んで引きずると床に傷をつけずに移動ができます。
またスチールフレームはカビが生えず、すのこやメッシュの底が通気性も良いのでお手入れも簡単です。
ただベッドとしては豪華さに欠け、長く使っているうちにきしみが発生しやすくなります。
その場合、接合部のネジが緩んでいる可能性があるので、増し締めすると音が減少することもあります。
3.レザー製(ウッド+レザーフレーム)

レザー製ベッドフレームと木製すのこの床板
レザーフレームと言っても心材は合板などの木質系です。その表面に、クッション材を挟みレザーで包み込んだものです。
レザーフレームは高級感が特徴のベッドフレームです。レザーには本革と合皮の2種類があり、それぞれ特徴が違います。
本革は使い込む程に色や質感が変化し、肌にも馴染みやすくなります。より高級感が出るのは本革ですが、価格が高価になります。
超高級ベッドは本革を用いますが、市販されているほとんどのレザーベッドは合成皮革です。
参考記事:失敗しない賢いレザーベッドの選び方
4.ファブリック製(ウッド+ファブリックフレーム)

ファブリック製(ウッド+ファブリックフレーム)
ファブリックフレームと言っても心材は合板などの木質系です。フレーム部分をクッション材を挟み込んで織物で覆ったもので、温かみのある風合いが特徴です。
硬いフレーム部分が露出していないので、身体をぶつけてケガをする心配もありません。お子さんやペットがいるご家庭に人気のタイプです。
ここまでがフレームの材質についての説明です。
次はすのこ部分の材質について説明します。
すのこってなんですか?

すのこ板
そもそも「すのこ」とは、やや太い木の角材(根太)の上に薄い板を直角に打ち付けたものです。
むかしはお風呂の洗い場で多く見られ、今でも押し入れの湿気防止などに使用されています。
工場や保管倉庫でもすのこ状のパレットが使われています。
普通のすのこと違うところは、モノや製品の保管や移動、運搬にフォ-クリフトが使われるため、リフターのフォ-クが刺さるように箱状になっているだけです。
すのこには隙間が設けられ通気性に優れているため、すのこの上に物を補完していても、長期に渡りかびたり湿気ったりしません。
ベッドもまた同じです。ベッドは倉庫よりさらに条件が悪いです。
なぜならベッドは、わたしたちが寝て無意識に汗を発散させているからです。
その汗の量は、一晩にコップ1~2杯にもなると言いますから、通気性が悪いベッドではカビやダニが発生しやすくなります。
そういうわけで、すのこはその構造によって通気性があり、湿気を溜めず逃がしてくれるのが大きなメリットです。
すのこの材料によっても特徴があります。
吸湿性が高く、カビが生えにくい性質を持つ桐(きり)や檜(ひのき)が、すのこベッドの素材としてよく使われています。

ベッドの床板、いろいろなすのこ板
すのこベッドに使われる4種類の木材
ベッドのすのこにはいろいろな樹木が付かwされています。それぞれに特徴があります。それらの特徴と評価は以下の通りです。
木材の種類と評価
| 桐 | ひのき | 杉 | パイン材 | |
| 湿気対策 | 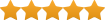 |
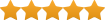 |
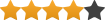 |
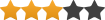 |
| 断熱性 | 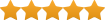 |
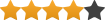 |
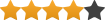 |
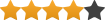 |
| 軽さ | 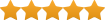 |
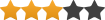 |
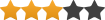 |
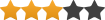 |
| 長持ち | 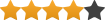 |
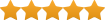 |
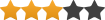 |
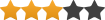 |
| 見た目 | 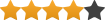 |
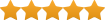 |
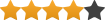 |
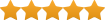 |
| リラックス効果 | 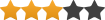 |
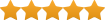 |
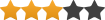 |
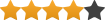 |
| 価格 | 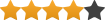 |
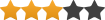 |
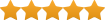 |
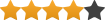 |
すのこに使われる材料は、木質系と、樹脂系があります。
ここでは木質系のすのこについて、さらに無垢材のすのこについて説明します。無垢材には集成材も含まれます。
どれも湿気に強い木材ではありますが、木の種類によってそれぞれの特徴があります。
代表的な木材は、「桐(きり)」「杉(すぎ)」「パイン材」「檜(ひのき)」の4種類です。
桐材

桐材
桐は、日本の気候風土にあった木材で、昔から様々な家具に使用されてきました。
岩手県の南部桐、福島県の会津桐などが有名ですが、もともとの原産地は中国と言われています。
昔から桐のタンスは有名です。会津では娘を嫁に出す時タンスを持たせるため、娘が生まれると桐を植えたそうです。
桐は生育が早いからそういうことが出来たのです。およそ20年ほどでタンス材になるまで成長するのですから、まさに娘と同じなんですね。
近年、国内での生産量は減少し、国産の桐材は超高級品でタンスを作るとなると200万円以上もします。
故に今は桐製の家具のほとんどが輸入された桐を使用しています。
中国を筆頭に台湾やアメリカ、ブラジル、パラグアイなどからも輸入されていますが、やはり中国産が多いです。
とても軽い
木材の中では一番軽い木が桐です。力のない女性でも組み立てや移動が楽です。
熱伝導率が低い
熱伝導率が低いというのは、要するに熱が伝わりづらいということです。昔から火事のときに桐タンスは黒焦げになったが、中の着物は無事だったという話が語り継がれています。外側が炭化しても中間で熱が伝わりづらいからです。
金庫の内部に桐材を使うのは、熱伝導率が低いため、もしもの時に中身を守るためと湿気結露を防ぐためです。
高級美術品を入れる箱も、このような理由で用いれられています。
熱が伝わりづらいということは、冬は冷たくならず、夏は熱くならないということなので、桐材は人に優しい木材なのです。
防虫効果
また桐材はタンニンを多く含むため防虫効果もあります。
タンスや、掛け軸など高級美術品の箱に用いられるのはそのためです。
桐材はお布団やマットレスが接触する、ベッドのすのこには、最も適した木材の一つなのです。
湿気に強い
湿度が高くなると膨張して湿気の侵入を防ぎ、乾燥すると収縮して通気性を良くします。
吸湿性が高いため、衣類の保管には最適とされる木材ですから、昔から和タンスや洋服ダンスに利用されてきました。
桐は自然の調湿機能をもっているので結露をしません。触ってもサラサラして、接触するものに優しい木材なのです。(ベッドにした場合、マットレスやお布団に湿気がこもりません)
杉材

杉材
すのこベッドの代表的な素材の一つである、杉(スギ)の名の由来は、真直ぐの木「直木」から来ていると言われています。
今や杉は花粉症の代名詞のように言われていますが、戦後山林育成に杉を多植したために起きている現象でしょう。
杉はわりと成長が早く、早くお金になると予想されため、日本中、至る山林が杉に覆われているのはそのためです。
ところがグローバル経済になると、世界中から安価な木材が輸入され、日本の杉は初期の経済構想から大きくはみ出して、こんにちを迎えています。
しかし、杉は割裂性がよいため、角材から板材までを作ることが容易です。従って、古来より重要な木材として重宝されてきました。
なんとか国産の杉で、家屋や家具が満たされる日が来ることを願うばかりです。
杉材は木目が真っ直ぐで、空気をたくさん含むため断熱性に優れ、住宅用建築材として広く用いられてきました。
また、細胞と細胞の間にたくさんの水分を含むことができるため、湿気を調整する機能にも優れています。
そのため、杉すのこベッドはベッドの木材としても非常に適していると言えます。
杉の短所は柔らかいので傷が付き易いということもありますが、それを云うなら桐などはとても耐えられません。
その桐でも珍重されるベッドのすのこでは、お釣りが来るくらいの強度があり十二分に通用する木材です。
杉には赤身(芯材)、白身(端材)が有ります、白身(しらた)の部分は腐り易いです(SPF材より耐久性有り)
赤い部分は硬く水に強いので家屋の骨組材に利用されます。
白い部分は水に弱いので、屋内で水掛かりしない場所に使われます。
杉の長所は材質が良い割りに安価なことです。そして、柔らかいので加工がしやすいことも特徴です。
パイン材

パイン材
パイン材は日本語では松ですが、実は沢山の種類があるのです。
日本でも松には、クロマツ、アカマツ、ゴヨウマツ、チョウセンゴヨウ、カラマツ、エゾマツ、アカエゾマツ、トドマツと8種類ほどあります。
その中の数種は建材や民芸品などその素材の性質に似合った使われ方をされています。
松の木は世界のいたるところで生息しています。北米。南米、北欧、オセアニア、東南アジアといろんな場所です。
もちろん同じ松科ですが、性質はそれぞれ違います。寒いところと暑い所、成長も違えば硬さも違いますし、幹の太さも違います。
世界では、松の種類は50種類以上と言われていますが、家具用材に向いている松は数種類で、イエローパイン、ホワイトパイン、ロッジポールパイン、ポンデロッサパインなどが多いです。
それぞれ特徴や癖があります。脂つぼが多くあったり、節が抜けやすかったり、表面の色が違ったりです。
一般的に上質で最も家具用材に向いているのはポンデロッサパインであるといわれています。
現実に多くのパイン材のアンティーク家具はポンデロッサパイン材が使われています。
その理由として、色変わりが綺麗で節に粘りがある点です。比べてみると良くわかりますが、ポンデロッサパインの節は独特なものがあります。
パイン材は最もベッドや家具に利用されている木材の一つです。
色味や薫りも良く加工がしやすいためパイン材のすのこベッドは多いです。
檜(ヒノキ)材

檜(ヒノキ)材
すのこベッドの代表的な素材の一つである、檜(ひのき)は、日本では建材としても最高品質のものとされています。
伊勢神宮の20年毎に行われる(建て替える)式年遷宮には厳選された檜(ヒノキ)が使用されます。
ヒノキの抗菌効果
木材を腐らせる腐朽菌(ふきゅうきん)には、代表的なものとしてオオウズラタケとカワラタケがあります。
ヒノキに含まれるαカジノールという成分からは、これらの菌の繁殖を抑える効果があることが分かっています。
αカジノールは抽出油に含まれる香り成分で、アロマオイルとしても利用されています。
ヒノキ風呂に人気があるのも、効能・効果が期待できるからです。リフレッシュ・リラックス効果は檜の香りの作用です。
消臭・脱臭・殺菌効果で生活臭を脱臭してくれるのは本当に嬉しい効能です。
ヒノキの防虫効果
ヒノキの成分にはダニやシロアリを防ぐ効果もあります。
ヒノキの木屑の中ではダニが死滅することが実験により確かめられ、カーペットの下に置く防ダニシートにはヒノキ精油が使われているものもあります。
これはαカジノールの効果とされています。
ヒノキの消臭効果
ヒノキ精油によってアンモニア臭を消す実験が行われ、効果が実証されています。
ヒノキ・トドマツ・ヒバから抽出した精油の中で、ヒノキ精油の消臭率は97%と驚きの数字を見せています。
これは、複数の成分が悪臭の成分と化学反応することで分解し、さらにヒノキのいい香りでマスキングすることで臭いを消しているのです。
ヒノキのリラックス効果
木材学会が発行する欧文学術雑誌「Journal of Wood Science」で発表された論文において、ヒノキの香りにはリラックス効果があることが報告されています。
ヒノキに含まれる香り成分αピネンを吸入すると、副交感神経系が優位となり、生理的リラックスがもたらされることが実証されたのです。
このようにヒノキの香りとリラックス効果の関係についても、研究機関で実証されているのです。
ヒノキが建築材として優れている理由
ヒノキが建築材として使われているのには、抗菌作用による防腐効果や、防虫効果だけではありません。
もう1つ注目されている大きな理由が、その強度特性です。
ヒノキは伐採後に200年間強度を増していき、伐採時の120%ほどまで強度は上がります。
その後長い年月をかけて非常に緩やかに強度は落ちていきますが、その低下具合は1000年で20%ほどです。
現存する世界最古の五重塔として知られる法隆寺の塔は607年に建造されたもので、建築材としてヒノキが使われています。
長期間強度を保ち続けるヒノキの特性が、このような歴史的建造物を支えているとも言えます。
以上すのこやフレームに使われる木材の特徴でした。
木質すのこのもう一つの特徴は「木の香り」です。
その正体は「フィトンチッド」と呼ばれるリラックス効果のある針葉樹特有の香りと言われています。
パイン材すのこやヒノキ材のすのこベッドは癒しのベッドと言えます。
すのこベッドに良い木材とは
それではお勧めのすのこベッドはどの木材が良いのでしょうか?といわれても一口にこれとはなかなか言えません。
それはすのこベッドはフレームとすのこの複合体だからです。フレームは合板のメラミン化粧ですのこが桐や杉ということが良くあるからです。
とここで終わってしまっては何にもなりませんね。いくつかお応えしましょう。
湿気対策を重視するなら桐かひのきをお選びください。
ご予算が許せばひのきがおすすめです。
桐もひのきもすのこの材質としては素晴らしい木材ですが、桐よりもひのきをおすすめする理由は、ひのきの方が耐久性に優れるからです。
ひのきの特徴として乾けば乾くほど強度が増すと言われています。
世界最古の木造建築物である法隆寺や、2000年の歴史を有する伊勢神宮でひのきが使われているのは偶然ではないのです。
すのこベッドフレームにはどのタイプのマットレスを使用できますか?
すのこベッドフレームは、ほとんど全てのタイプのマットレスと組み合わせることができます。
すのこベッドに最適なマットレスは、主に個人的な好みに依存しますが、考慮すべき重要な要素がいくつかあります。
スプリングマットレス
このタイプのマットレスは約2世紀にわたって使用されてきましたが、技術革新により、より現代的なデザインと機能が追加されています。
スプリングマットレスは、大きく分類して、ボンネルコイル、ポケットコイル、連続スプリング、オフセットコイルなどがあります。
このタイプのマットレスは、大手のブランドマットレスメーカーの主力商品です。
コイルマットレスは通気性に優れ、快適なサポートを提供するため、すのこベッドに最適です。
単独で使用することも、ボックススプリングと組み合わせて使用することも可能です。
■ボンネルコイルの代表メーカー
・シーリ
■ポケットコイルの代表メーカー
・シモンズ
・サータ
・日本ベッド
■高密度連続スプリングの代表メーカー
・フランスベッド
低・高反発マットレス
低反発マットレスは、地球を周回している間、宇宙飛行士を快適に保つためにNASAによって設計されました。
ご想像のとおり、それらはかなり特別です。一時期流行りましたが今では大分廃れました。
その理由は、宇宙と地球では重力の関係で使い勝手がものすごく違うためです。宇宙では重力がないため、あんなには沈まないのです。
そんなことから、今の主流は高反発マットレスに移行しています。
マットレスは、体にぴったりとフィットする高密度フォームでできており、体の接触点への圧力を軽減します。
起き上がってベッドから出ると、フォームは、永久的なくぼみが残らず緩やかに復元します。
低反発マットレスもすのこベッドに最適です。
ただし、メモリフォームは時間の経過とともにすのこの間隔が広いと落ち込むので、すのこ間のスペースを最小限に抑えるか、ボックススプリングを使用するかにしましょう。
■ウレタンマットレスの代表メーカー
・テンピュール
・マニフレックス
■低反発マットレスの代表てきなもの
・テンピュール
・トゥルースリーパー
■高反発マットレスの代表的なもの
・マニフレックス
・エアウィーヴ
・モットン
ラテックスマットレス
アレルギーや喘息に苦しんでいる場合は、ラテックスマットレスが最適なマットレスです。
ラテックス層により、マットレスにダニや汚れが付着せず、ぐっすりとお休みいただけます。
ラテックスマットレスは、フォームの一種ですが、メモリーフォームよりも剛性があります。
十分な安定性も必要ですが、メモリーフォームよりわずかにすのこの間隔が大きいベッドにも対応できます。
このタイプのマットレスは。メモリーフォームよりも少し構造化されているため、それほど多くのサポートは必要ありません。
ただし、あまりにもすのこの間隔が離れている場合は、ボックススプリングの使用を検討することをお勧めします。
ハイブリッドマットレス
ハイブリッドマットレスは、他のすべてのタイプのマットレスの要素を組み合わせたものです。
それらは、メモリーフォーム技術、ラテックス層、またはその両方、およびポケットスプリングを組み込んでいることがよくあります。
そらはすのこベッドフレームのための優れた選択肢です。
すのこで注意すべきこと
よりサイズが大きいベッドでは、ベッドの縦方向の半分にあたる中央にサポート(梁)が必要です。
中央サポートが付いていないダブル、キングサイズ、またはスーパーキングサイズのベッドを見つけた場合は、注意が必要です。
大きなベッドの幅全体に梁の無いすのこを使用すると、圧力が加わるとたわみ、へたをすると破損に繋がります。
すのこ間の隙間
すのこの板の隙間は7〜10cmをはるかに超えてはなりません。
それらの距離がこれ以上大きい場合、マットレスが部分的にサポートがなくなり機能を十分に発揮できません。
この場合は、ボックススプリングの使用を検討することをお勧めします。
つまりこの隙間は小さいほどマットレスのスプリング(クッション)効果や衝撃吸収性能は発揮しますが、あまりにも狭いと通気性がそがれ湿気が溜まります。
すのこの張り方
すのこの張り方は縦張りと横張りがあります。
これは見た目の好みでという事になります。
強度については、すのこ板の幅と厚さ、すのことすのこの間隔、すのこ板を打ち付けた根太、そしてベッドフレームの根太掛かりなどが影響します。むしろそっちの方に気を配りましょう。
すのこは、マットレスを受け止めるベースです。あまりにも間隔が広いすのこは、マットレスの機能を十分に発揮できません。
ですから、選ぶことに妥協し、あまりにも間隔が広いすのこは、大したことではないように見えるかもしれませんが、マットレス性能にどれほどの違いを生むかは驚くべきことです。
まとめ
すのこベッドは日本の気候風土に合っった素晴らしいベッドです。しかし、ベッドに使用されるすのこの材料と仕上げの質には結構な開ききがります。
すのことすのこの隙間は大きいほど通気性に優れますが、マットレスの性能を著しくし阻害します。反対に狭いとマットレスのクッションやバンでの動きは快適になりますが、通気性に劣ります。そのへんの加減は難しいですが、すのこの隙間を7~10cm以上に広げないことです。
-neruco-欲しいベッドが必ず見つかる、国内最大級のベッド通販専門店。ベッドコンシュルジュネルコ-neruco-
インターネット最大級【アイテム数3,000点以上】おしゃれなベッド・寝具多数掲載! 取り扱いメーカー/フランスベッド/ サータ ドリームベッド/ 東京ベッド/ パラマウントベッド/日本ベッド/ウォーターワールド /Platz(プラッツ介護ベッド)/ /Sealy(シーリー)/ 東京スプリング工業 /東京西川 昭和西川